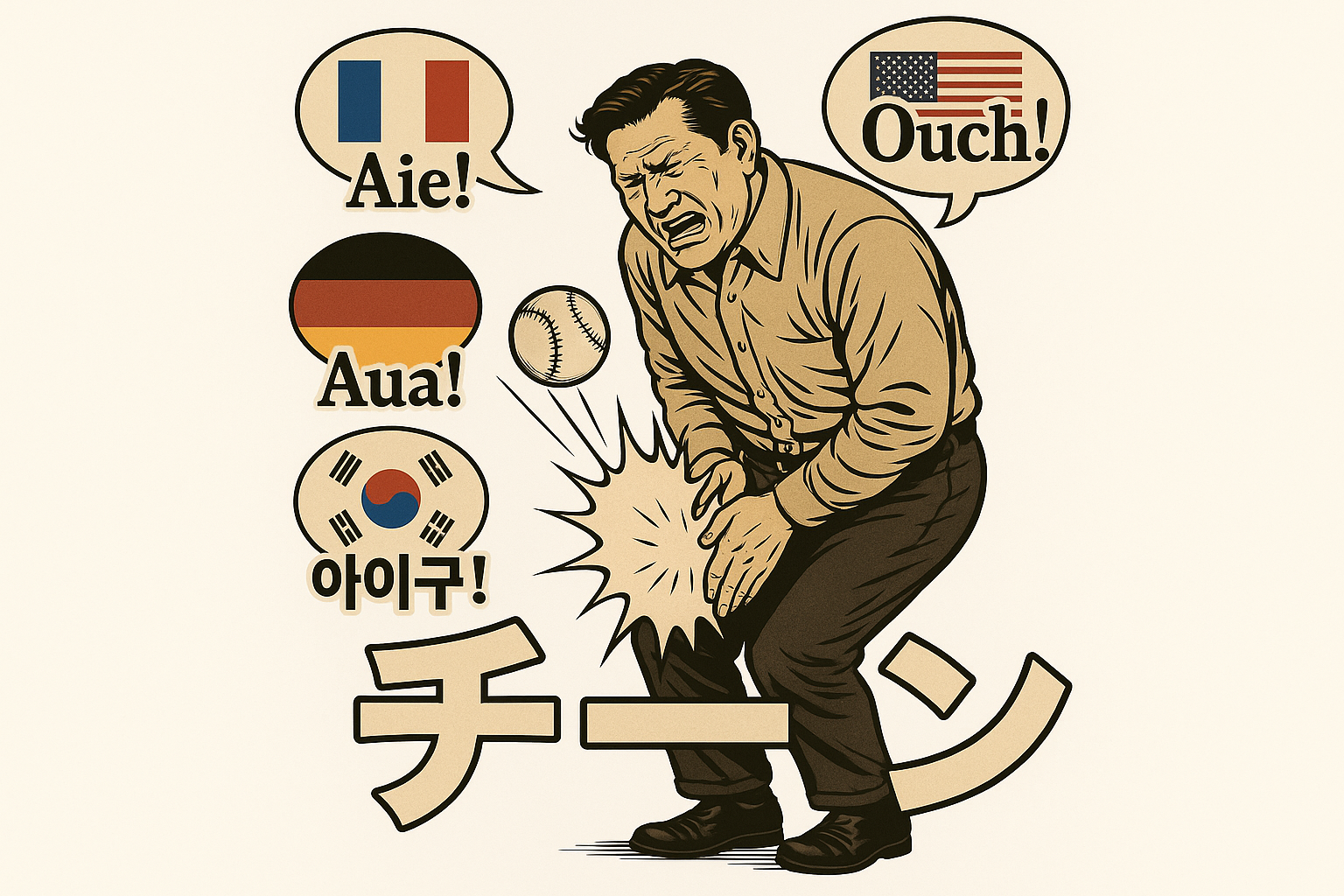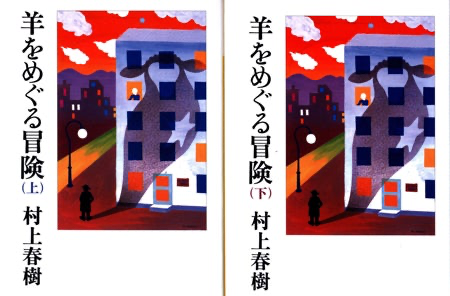踊るということ「ダンス・ダンス・ダンス」
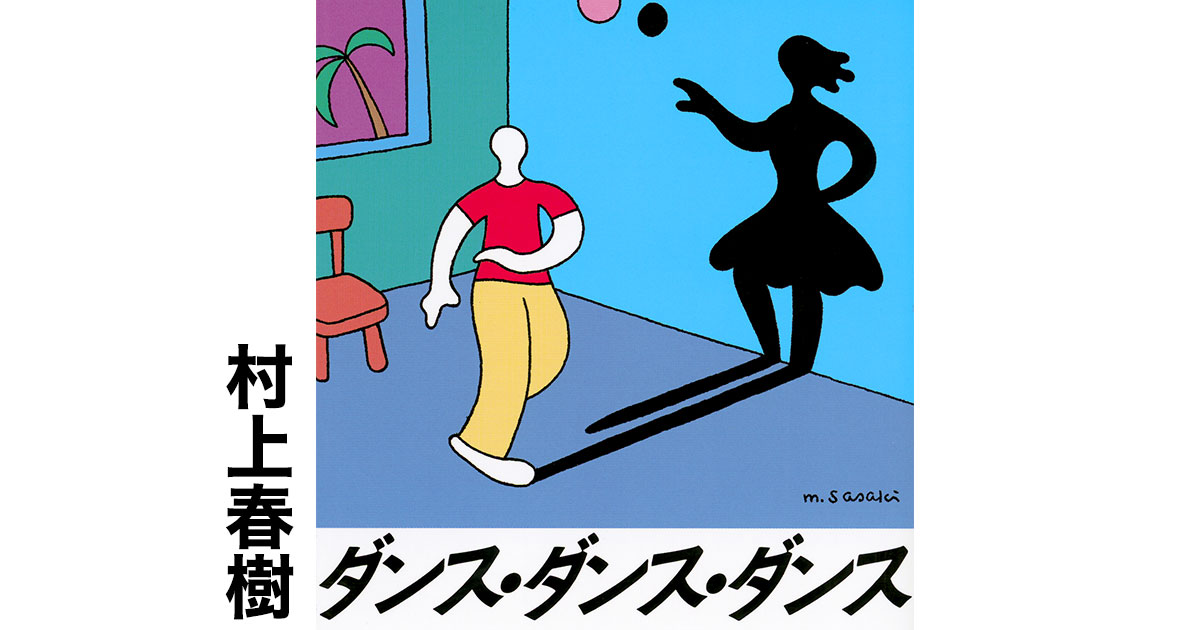
『ダンス・ダンス・ダンス』という小説がある。
村上春樹の作品世界を語るうえで、この『ダンス・ダンス・ダンス』はひとつの分岐点にあたる作品かもしれない。
1979年のデビュー作『風の歌を聴け』に始まり、『1973年のピンボール』『羊をめぐる冒険』と続く、いわゆる“鼠三部作”の最終章として書かれたのが本作である。ここまではある種の私小説的な語りと、幻想性、都市の孤独がゆるやかに絡み合う作風が特徴だった。
しかしその流れは、1987年の『ノルウェイの森』によって大きく変わる。リアルな恋愛と喪失を描いたこの作品は、従来の春樹ファンだけでなく、広い読者層を取り込む大ベストセラーとなった。いわば“国民的作家”としての村上春樹が誕生した瞬間である。
村上春樹としては今までの作風とは異なる作品が大きな反響を受けたことに些か違和感を覚えたようだ。しかしながら村上作品の中で『ノルウェイの森』だけは読んだことあるという読者も多いのもまた事実である。
本人にとってこの成功は、決して居心地の良いものではなかったようだ。『ノルウェイの森』出版後、村上春樹は日本を離れ、しばらくの間海外で生活を始める。そうした“逃避”と“再構築”のなかで翌年1988年に生まれたのが、『ダンス・ダンス・ダンス』なのだ。(もちろん執筆自体は日本時代から行われていたと思うが)
この作品では、再び“僕”が語り手となり、過去の物語をなぞるように、失われたものを探す旅が描かれる。しかし、そこにあるのはかつての幻想的な牧歌ではなく、バブル経済下の東京の冷たさ、企業社会の闇、そして表層的な豊かさに満ちた都市の「空白」である。
そういう意味で、『ダンス・ダンス・ダンス』は、“春樹的なもの”の原型と、“ポスト・ノルウェイの森”のリアルな語り口の中間に位置する、ある種の転換点のような作品だといえるだろう。
語り手である“僕”は、失踪した女性を探しながら、「ドルフィン・ホテル」を再訪し、数々の人物と出会い、ときに幻想と現実のあわいを彷徨いながら、少しずつ物語を進めていく。
物語の構造自体はそこまで複雑ではない。だが、そのなかに漂う“雰囲気”は強烈である。それを感じるために読者は何度もこの本の表紙をめくるのである。
村上作品の多くで、現実の風景のなかに溶け込むように挿入される“異物”の存在がある。それは本作では「羊男」だったり、「闇の中の部屋」だったりする。村上春樹の描く世界では、それらが特別なものとしてではなく、日常と地続きのものとして描かれている。
本作で度々出るフレーズがある。
“踊るんだ、踊りつづけるんだ”
タイトルでもダンスという言葉に特別な意味を置いているように、このフレーズは本作を象徴している。
何があっても、自分のリズムを手放さずに、動きつづけること。誰かに見られていなくても、音楽が鳴っていなくても、身体を止めずに踊り続ける。それがこの物語の、“僕”の伝えたいことである。
この物語の語り手である“僕”は、どこか投げやりで、諦観を持ちながらも、人間関係のなかに微かな温度を求めつづけている。
ユミヨシさんというホテルの女性スタッフとの関係、元恋人キキの記憶、天才少女ユキとの交流、そして五反田くんとの関係など、それぞれが断片的に進行していくが、それぞれの人物の中に僕は居場所を見つけ、僕の中にも彼らの居場所を与え続けている。
村上春樹という作家は、「失われた何か」と「それを追う人」の物語を描くことが多い。『風の歌を聴け』に始まり、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』を経て、本作『ダンス・ダンス・ダンス』へとその主題は継承されている。
ただ、『ダンス・ダンス・ダンス』では、その“喪失感”の描き方に、どこか淡さと明るさが混じっているように感じられる。
それは、80年代という時代の空気感とも重なっているのかもしれない。バブルに突入する直前の東京、表層的には明るく、豊かで、すべてがうまくいっているように見えている。しかし、その奥底では、何かを失い続けているような感覚がある。(私はバブルを経験していないのであくまで想像だが)
作中の登場人物たちは、みなそれぞれの“闇”を抱えながら、それでも日々を生きていく。
そして物語の後半で、ある事件が起きる。
詳しくは書かないが、それによって“僕”は再び、自分自身と向き合わざるを得なくなる。
その過程で、“踊ること”の意味が、少しずつ変化していくように感じた。
最初は逃避のように見えた“踊り”が、やがて、現実と向き合うための手段へと変わっていく。
『ダンス・ダンス・ダンス』という作品を含め、“羊三部作”は村上春樹のなかでも、比較的“読みやすい”部類に入るだろう。物語は比較的直線的であり、登場人物も比較的ポップである。
だが、だからといって軽い作品かというと、答えはNoである。
その奥には、次の静かな問いがずっと漂っているように感じる。
「僕たちは、なぜ生きるのか」「なぜ、繋がろうとするのか」
そしてその問いに対して答えは本作では示されない。
だが、それでも“踊りつづけるしかない”という一つの姿勢だけが、最後に残る。
ここで“羊男”という存在について、改めて考えてみる。
物語の中では、突拍子もない着ぐるみのような姿で現れながら、妙に理知的で、人懐っこく、そしてどこか深い悲しみをまとっている。彼の語ることは一見おとぎ話のようでいて、実のところは、主人公の内面を映し出す鏡のようでもある。
例えば、あの密室的な空間で主人公と羊男が交わす静かな会話は、誰かと話しているというよりも、自分の中の何かと対話しているような感覚に近い。
羊男は現実と幻想のあわいにいる存在として描かれている。それはある種の“魂の保管者”のようにも思える。
何かを見失いそうになったとき、あるいは何かが壊れかけているときに、その存在がふっと現れる。そして、曖昧な言葉でそっと支えてくれる。
それはもしかすると、私たち一人ひとりの中にも棲んでいる存在なのかもしれない。世界が少しだけ寒くなったとき、何かを守るために心の片隅に現れる誰かなのかもしれない。
『ダンス・ダンス・ダンス』に描かれる80年代の東京はどこかフィクションのような風景として描かれている。高層ビルが林立し始め、街には情報と欲望があふれ、夜のネオンが終わりなき労働と孤独を照らし出している。
この物語のなかで、主人公はホテルやバーやレンタカーを乗り継ぎながら、終わりのない移動を続ける。それは“失われた何か”を追い求める旅でもあるが、同時に、“この時代の空虚さ”と向き合う旅でもあったように感じられる。
今の東京で『ダンス・ダンス・ダンス』に出てくる東京の風景を重ねることは難しいかもしれない。しかしながら、1980年台の東京も2020年代の東京であっても、我々は変わらず一人なのである。結局一人で生きていかなければならないのである。
そして世界とつながり続けるためには踊るしかないのかもしれない。
自分のリズムを守りながら、誰にも見えなくても踊り続けなければならないのである。
ダンス・ダンス・ダンス!