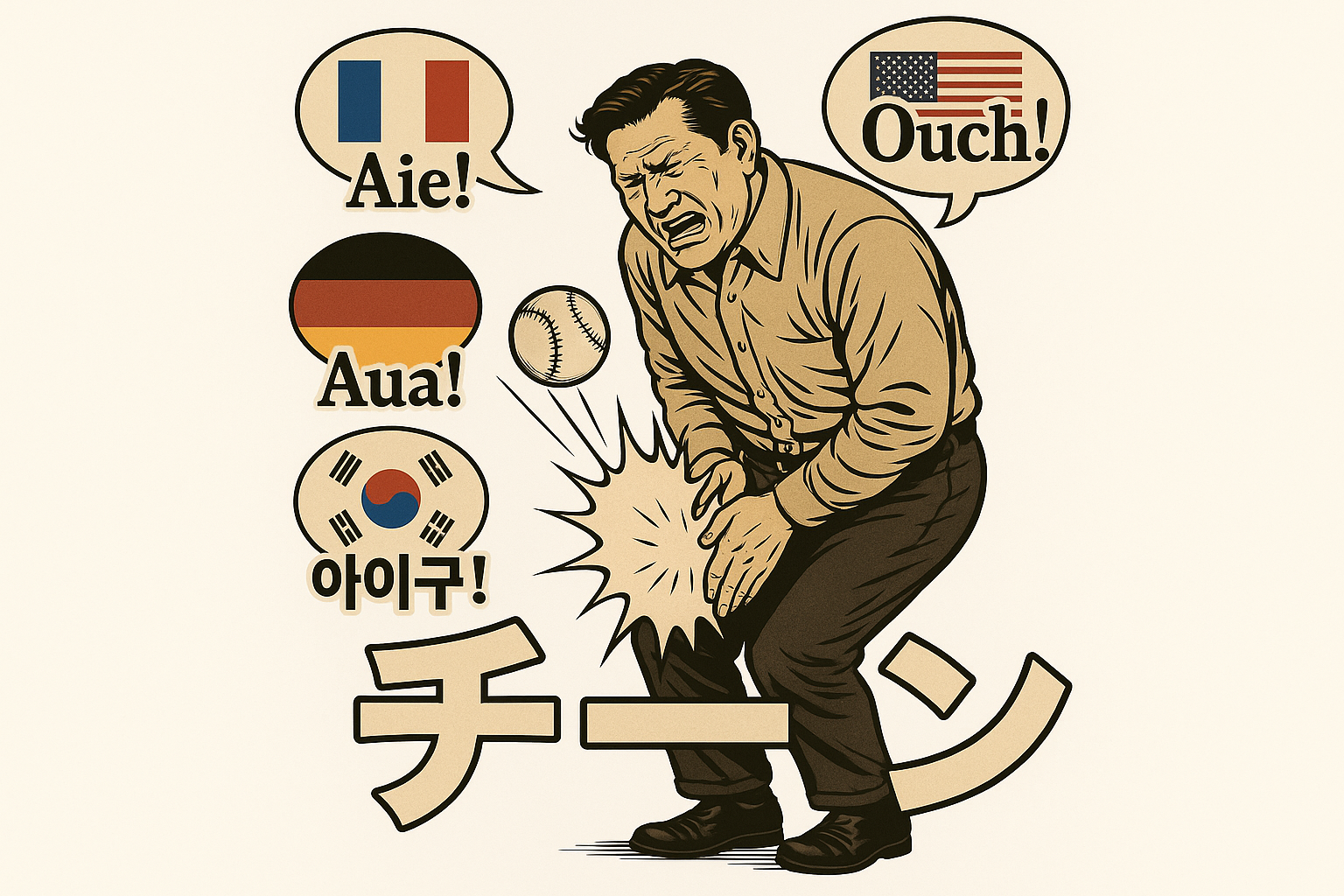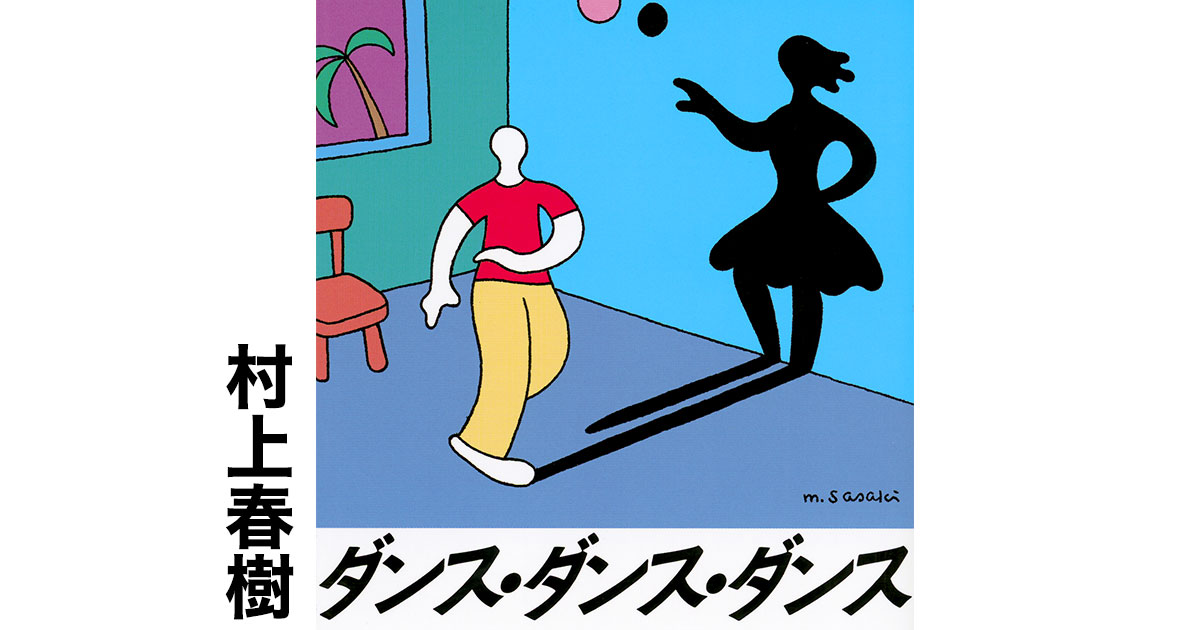『ノルウェイの森』─喪失の森の中で

「死は生の対極ではなく、その一部として存在している」
『ノルウェイの森』を読む上でこの一文は大きな意味を持つ。この一文を僕らに伝えるために『ノルウェイの森』は書かれたと言ってもいいのかもしれない。
村上春樹の文体は、この小説においても(相変わらず)一貫して静謐で、過度に説明することを避けている。読者は、行間に宿る思考や感情を自らの中で反響させながら、主人公ワタナベの目を借りて死者と、生き残った者と、自分自身と向き合っていく。
失われるものの重み、その後に残る“空白”
物語は三十七歳になったワタナベが、ハンブルク空港でビートルズの「Norwegian Wood」を耳にした瞬間から始まる。その曲はワタナベにとって特別な曲だった。無防備な耳に届いたその旋律が彼の心を容赦なく揺らし、閉じ込めていた記憶を一気に蘇らすことになる。「Norwegian Wood」が彼を三十七歳から十八歳へと瞬く間に引き戻したのだ。十八歳の頃の東京。青春と喪失の原風景への入口。すべての物語の起点である。
音楽というものが、ただの記号ではなく、心の奥に眠っていた感情を呼び起こす一種のトリガーであるように。「Norwegian Wood」の旋律によって開かれたワタナベの記憶の中に僕らは足を踏み入れていく。
この小説は多くの喪失を描いている。直子の死。キズキの死。多くのものが死んでいく。突如として訪れる別れは、あまりに唐突で、まるで説明を拒むかのように存在している。当然だが、死に理由などない。理由などないのだ。問いかけてももちろん何も返ってはこない。それが死というものだ。ワタナベはその理由のなさに耐えながら、いつか忘れてしまうんじゃないか、ということを恐れながらも、それぞれの死者を自らの胸に刻み込んでいく。
彼の中で静かながらも死者たちは息づいている。彼らの声や仕草、残していった余韻。それらは彼の内側で沈黙のまま生き続けながら、彼の存在そのものを支えている。「死者を背負って生きていく」これは人間にとって避けることのできない宿命なのかもしれない。死はワタナベの背中にも影のように貼りつきながら、彼を少しずつ前へと押し出していく。
誰にとっても十八歳から二十代前半というものは、非常に繊細な時間である。(もちろん私にとっても思い出したくことのない数々のオンパレード。地獄のような期間である)
心はまだ未完成で世界の輪郭ははっきりしていない。希望と絶望は混ざり合い、現実と夢の境目もはっきりしない。自分と他人の区別すら曖昧な期間である。ワタナベもその揺らぎの中に身を置いていた。彼は自分の存在を誰かの不在を通じてしか証明できないと感じていたのかもしれない。「そこに存在していた」過去の重さと「そこにもう存在していない」現在の空洞とが、彼に波のように押し寄せていた。
ワタナベが「Norwegian Wood」を聴いた時の感情、その時の感情を僕らも知っている。「ある瞬間」その瞬間はワタナベと同じように何かの曲を聞いた時かもしれない。もしくは何かの香りがフッと通り過ぎた時かもしれない。その「ある瞬間」に誰かの顔や、交わした言葉の断片がフラッシュバックすることがある。その瞬間に僕らは、過去に戻ることができる。過去の記憶の中で死者に会うことができる。そう考えると死者は記憶のなかで生きているのかもしれない。そういった死者との一瞬の共生のなかで、ワタナベは生の意味について考える。
痛みを抱えながらも前進していく。そうしてワタナベは「生きる」ことの意味について考えていく。もしかしたらその行動こそが「生きる」ということの正体なのかもしれない、と。
永沢という存在―紳士であるということ
『ノルウェイの森』の中で異質な男がいる。
もちろん永沢である。
私が初めてこの本を読んだとき永沢は年上の男だった。その生命力、パワーに大きな憧れを抱いたものである。永沢より年上になって改めてこの男を見ると、少し異なる印象を覚える。ワタナベよりもずっと繊細で弱い男に私には写った。
永沢という男は主人公ワタナベの下宿先に住む先輩である。東大法学部に通いながら外交官を目指している。ルックスも申し分なく、巧みな話術も持ち合わせている。要はカリスマとしてこの作品に登場する男である。そしてワタナベにとっては数少ない、日常を共有する中の一人だ。だがその佇まいはワタナベの周囲にいる人物、繊細で感情の起伏に翻弄される人物たち(ここではもちろん直子やミドリ、レイコである)とは明らかに異なっている。
永沢は極端なまでに合理的な男として登場する。無駄な情緒を排し、自らの感情にも他人の感情にもほとんど頓着しないように振る舞う。彼にとって人生とは克服すべき階段のようなものなのだろう。
「このばかでかい官僚機構の中でどこまで自分が上にのぼれるか、どこまで自分が力を持てるか、そういうのを試してみたいんだよ。」
「ゲームみたいなもんさ。俺には権力欲とか金銭欲とかいうものは殆どないんだ。ただ好奇心があるだけなんだ。」
コレらはもちろん永沢のセリフである。外交官になるべく、努力を淡々と続け、規則正しく、あらゆる感情的な出来事から身を遠ざけている。おそらく彼には人生という1つのゲームの中で自分がどこまでたどり着けるのかそれを知りたいだけなのだろう。そこに他の感情が入り込む余地は無いのかもしれない。一方でその生活は、まるで「感情の外側」に自らを置くことで、自分を守ろうとしているようにも映る。
そしてそれらの行動を促している永沢なりの行動規範がある。それは「紳士であることだ」ということらしい。もちろんここで指している紳士とはコリン・ファースのような男でもなければジェームズ・ボンドでもない。そして永沢はこう続ける「やりたいことをやるのではなく、やるべきことをやるのが紳士だ」と。
永沢との最初の出会いは、ワタナベが学生食堂で『グレート・ギャツビー』を読んでいたときだった。ふいに声をかけてきた永沢は、ワタナベの読む本に目をとめ、「『グレート・ギャツビー』を3回読む男なら俺と友達になれそうだな」と言ってワタナベと永沢は友達になった。彼の影響で『グレート・ギャツビー』を手に取った日本男児がどれだけいるだろうか。もちろん私もその中の一人である。
『グレート・ギャツビー』は夢と喪失に取り憑かれた一人の男の物語である。ギャツビーは手の届かない過去と愛に執着し、やがて破滅へと向かうことになる。村上春樹はギャツビーと永沢を重ねて表現したかったのだろうか。恐らくそれはNoだろう。永沢は、ギャツビーのような「熱」を持ち合わせてはいない。永沢は最初から夢を見ようとせず、執着を嫌悪し何かを「失うこと」さえ、最初から排除しているように映る。おそらく彼はギャツビーを評価しても決して自分と重ねたりはしない男である。むしろその対極にある生き方を選んでいる。
そんな永沢が、物語の中盤、ワタナベとの別れ際に放った言葉がある。
「自分に同情するのは下劣な人間のやることだ」
初めてこの本を読んだとき、私もワタナベと同じよう最初はピンとこなかった。しかしながら時が経ち、改めてこの言葉に触れた時、ひどく永沢に感心したものである。だが一つ疑問に思うこともある。コレは彼の強さの証の一つなのだろうか、ということである。この言葉は強さの証というよりも、感情を切り捨てることによって成立する一つの自己防衛だったのではないか。自分の弱さを見つめるのではなく、排除することを彼は選択していた。だがそこに人としての深みが出るのだろうか。本当に彼は「強い」人間なのだろうか?
永沢という人物は、物語のなかただ淡々と前進していく。その前進という変化は他の登場人物の変化と180°異なっている。ただ淡々と己の哲学に従って生きていく。だからこそ彼の存在は、ワタナベにとっても、読者にとっても、「強さ」とは何かを問い直させる鏡のような存在になっている。
強さとは、感情を排除し合理的に生きることなのだろうか。誰にも依存せず、誰にも期待せずに生きることなのだろうか。それとも、痛みや喪失にさらされながらもそれに向き合い、誰かを思い、心を通わせることこそが本当の強さなのだろうか。
永沢という男は、おそらく自分の脆さを見せることを、死ぬほど恐れていたのだ。だからこそ、感情を封印し、孤独を選び、あらゆる人間的なつながりを限定することでしか、生きていく術がなかったのかもしれない。
彼の冷たさは彼にとって必要なものだったのだろう。それが彼なりの、生きることの形であり、誰とも共有できない一つの痛みだったのかもしれない。
直子という迷路―沈黙の中に生きる女
『ノルウェイの森』という物語の核にいるのが、直子という女性である。
彼女は主人公ワタナベの親友・キズキの恋人であり、彼の死後、残された痛みとともに再びワタナベの前に現れる。ワタナベにとって直子は、単なる恋愛の相手というよりも、死者の影と共に存在する特別な人として写っている。そして永沢が「強さの象徴」であるならば、直子は「弱さの象徴」だろう。
直子はひどく繊細で、壊れやすい人物として描かれている。
表面上は穏やかで優しく、物静かで魅力的にも映るが、その内側には深く静かな闇が広がっている。キズキの死が彼女にもたらした傷は根深く、彼女の時間はあの日から止まったままである。東京で再会してからの二人は、長い距離を言葉少なに歩くことになる。その沈黙はときに親密さであり、ときに拒絶の一種だったのかもしれない。
やがて迎えた直子の二十歳の誕生日の夜――ワインを分かち合い、彼女は泣き、言葉はほどけ、境界は崩れ落ちる。翌朝、彼女は姿を消し、間もなく山の療養施設(阿美寮)に入ることになる。そこはまるでこの世界から切り離されたもうひとつの現実で「沈黙」が支配している場所として表現されている。直子はそこで、レイコやスタッフの手助けを受けながら静かに日々を重ねるが、そこから彼女の心情が大きく変化することはない。
直子の言葉ひどく曖昧で、繊細なものとして描かれている。
ときに言葉は意味を結ぶことなく、涙だけが流れることもある。彼女は誰にも身体を預けることができない。その孤独はひとりの少女の気まぐれではない。深い傷の形なのである。
小説の中に「見えない井戸」という比喩が繰り返し現れる。
草原のどこかに口を開く深い井戸である。足を踏み外せば戻れないかもしれない場所。その不穏な想像は、直子の内面を表したものである。ワタナベも直子もその井戸の場所を知っているのだろう。そして直子はその井戸の下への確実に引かれていくことになる。ワタナベはその縁に立ちながら、手を伸ばし続けるしかない。
「死は生の対極ではなく、その一部である」
この言葉は、ワタナベの胸中に宿る認識として記述される。直子は死という現実を受け入れる。死は生の対極ではなく、生の延長線上に死が置かれていることを受け入れている。
そして作中に出てくる、手紙の往復は、ふたりを繋ぎ止める唯一の方法だった。
紙の上では直子の気持ちは丁寧に描かれている。文字は距離を縮め、同時に距離を可視化する。ワタナベは救いたいと願い、直子は救われたいと願っている。しかし互いの手は再び交わることなく二人の往復は静かに終わることになる。
最終的に直子は、自ら終わりを選ぶ。
その選択は脆く、そして清らかに描かれている。彼女は壊れた部分を誰にも委ねず、修復もせず、そのまま抱えて生きようとした。しかし、抱えつづけるための力が尽きることも、また生の一部なのかもしれない。
直子がワタナベに残したものは誰かを想うということの静かな余韻だった。それは直子が長年キズキに対して抱いていた感情の一つかもしれない。
彼女は最後まで他者と完全には交われなかった。それもある意味ではキズキと同じなのかもしれない。そして彼女が「そこにもう存在していない」という現実はワタナベの中に深く沈み込んでいく。
終幕─“どこにいるの?”という呼びかけ
『ノルウェイの森』のラストシーン。電話口の向こうでミドリが「今どこにいるの?」とワタナベに尋ねる。もちろん、それは単なる位置の確認ではない。受話器を握るワタナベは、その言葉を胸の内で反芻しながら、自分自身に同じ問いを向け直す。「僕は今、どこにいるのだろうか?」と。
繰り返すが、この問いは、地図上の座標を求めているわけではない。キヅキの死。直子の死、レイコと過ごした夜。それらの放浪の果てに、ワタナベは「場所」の手触りを失ってしまっている。彼の世界では、自分の現在地を地名で判断することができなくなってしまっている。他人との関係を通して認識している。しかしワタナベの周りの人間はミドリを除いてみんないなくなってしまった。最後に彼を世界と繋ぎ止めているのはミドリだけだった。そのミドリの「今どこにいるの?」はまさにその彼を見えない井戸から現実の世界へとを取り戻そうとする呼びかけなのだろう
物語の冒頭では、ビートルズの一曲が深く沈み込んでいた記憶の扉を押し開き、ワタナベを十八歳へと連れ戻した。ラストでは、音楽ではなく“声”が彼を現在へ呼び戻す役を担っている。「Norwegian Wood」の旋律が過去を開き、ミドリの声が彼の現在を確かめるトリガーとして表現されている。
このエンディング、ワタナベは場所を伝えることができない。しかしながら呼びかけに応じようとする意志は残っている。
ワタナベは今、喪失の森で迷子になっている。正しい出口を知らない。しかし誰かの声に応えるという単純な行為が最初の一歩になるだろう。森を抜ける道は地図ではなく、声と声のあいだに現れる。
もちろん、終幕の「どこにいるの?」僕らに向けられた言葉でもあるだろう。
彼らと同じような喪失のあと、深い森の中で自分の居場所を見失ってしまった時、私たちはどこに立っているのだろうか。きっとそれは地名ではなく、誰の声に応えるのかという形で、自らの場所を判断するのだろう。呼びかけがある限り、喪失の森から抜け出すことはできるのだ。